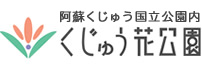こころノベル【ハート物語】
「二十歳の誓い〜
笑顔という名の人生バトン」
(どんな時も笑顔で生きて行く!
それこそが母の教えだから!)後篇
梅雨のジメジメした日々は
もうとっくに過ぎて、
日に日に暑さが増してきた
と思ったのも束の間、
ジリジリとしたある夏の日の夜、
今日は地元でもとっておきの
夏イベント「七夕まつり」。
商店街のアーケードに
飾り付けられた「七夕飾り」を
「綺麗だね〜」と言って、
楽しそうな笑顔の
沙耶さんの横顔に
何故か癒されている自分がいた。
試験に落ちた後、
専門学校は卒業を迎えて、
ここのところ、
いつもバイト先の施設と、
母の入院している病院との
往復に追われている僕に、
「たまには気分転換しないと」って、
沙耶さんのお誘いで、
久しぶりに世の中の
賑やかな空気を吸って、
何だかずっと抑圧されてたこころに、
ちょっぴりウキウキした爽快感が
流れ込んでいくのを実感していた。
「あっ!彰吾君!」
声のする方に振り向くと、
学生時代の同期の
女の子達が浴衣姿で、
ニヤニヤしながら
近付いて来た。
うちの一人が、
「こんにちは!」って、
沙耶さんに挨拶した。
沙耶さんも、
「こんにちは!」って、
笑顔で返した。
他のひとりが、
「詳しい事はLINEで聞くから!」
と言って、皆で手を振って去っていった。
沙耶さんが、
「可愛い子たちだったね」って言って、
チラッと僕の顔を窺い見た。
「そうっすかね!」と、
ちょっと素っ気なく応えた。
そう言っておいた方が無難な気がした。
「行こっ!」と言って、
沙耶さんが僕の腕を組んで
歩き始めた。
びっくりしたけど、
沙耶さんの腕の温もりに
ちょっとドキドキしていた。
しばらく歩いていると、
携帯の呼び出しが鳴った。
母の入院している病院からだった。
「あっ、〇〇さんの携帯ですか?」
「ハイ、そうです!」
「〇〇先生が、
すぐに来て貰えますかとの事です!」
「アッ、わかりました!」
ちょっと浮かれ気分だった僕は、
急に現実に引き戻された。
すいません沙耶さん、
「病院からすぐに来て下さいって。」
「わかった!行こう!」
と言いながら、
沙耶さんの表情が、
少し険しくなった様に見えた。
緩和ケア病棟の応接室で
しばらく待っていると、
担当の先生と看護師さんが、
「お待たせしました、」
と言いながら入って来た。
早速先生から、
今の母の病状説明と、
これからの方針が
詳しく述べられて、最後に、
少し先生の表情が硬くなって、
「ご本人がしっかり意識があって、
息子さんとお話し出来るのは、
今日が最後になろうかと思います。
今から一時間程ですが、
ゆっくりお話しなさって下さい。」
二人で病室に向かった。
静かにドアを開けて入ると、
母が気付いて微笑んでくれた。
「お母さん、と言って、
二人で母の枕元に寄り添った。
母が、静かに手を動かしたので、
そっと手を柔らかく握った。
その手は細く柔らかく、
とても温かかった。
自然に涙があふれ出た。
溢れて溢れて仕方なかった。
沙耶さんが涙を零しながら、
そっと僕の頬に、
ハンカチを添えてくれた。
「沙耶ちゃんありがとう!」
と、母が微笑んだ。
続けて母は、
「何で泣いてるの?」と言って、
悪戯っぽく僕に微笑んだ。
「何でもないよ!」と言って、
「お母さんはどうしていつも、
笑顔でいられるの?」って聞いた。
すると母は微笑みながら、
「大好きな二人が、
目の前に居るからよ!」
「だから今、幸せなの!」
「いつもそう思って生きて来たのよ!」
そう言いながら、少し母の手に
ちからが入った気がした。
母の言葉は、僕には深くて重かった。
「そうなんだ!」と言って、
母の言葉を噛み締めていると、
母が沙耶さんに言った。
「沙耶ちゃん、彰吾をお願いね!」
そう言って、微笑んだ。
沙耶さんは、「ハイ!」と、
母に微笑み返した。
そして沙耶さんは、
「ふたりでゆっくりね!」
そう言って、
静かに病室の外に出ていった。
それからふたりでゆっくりと、
最期の親子の会話を交わした。
「生まれて来てくれて、ありがとう!
幸せだったよ!」
それが母からの最期の言葉だった。
告別式は、僕の20歳の誕生日だった。
棺の中の母の顔は、とても綺麗で、
穏やかに微笑んでいるように見えた。
それからは、様々な法事に追われ、
夏は去り、秋は過ぎ、
母が去ってすぐは、
部屋の中は
静けさだけに
覆い尽くされていた。
最後は見守るだけに
なった母が去ると、
部屋の中は急に
寂しさを纏った
静けさだけに
覆い尽くされた。
ふと一人になった寂寞感に
押し潰されそうになった僕の、
常に沙耶さんは僕の傍で
優しく微笑んで寄り添ってくれた。
そしてチラチラ雪舞う冬を迎え、
2度目の国家試験も無事に終え、
暖かい春の陽射しに包まれて、
今日は、父母の眠る墓前に、
ようやく嬉しい報告に、、。
島に渡る連絡船のデッキで、
「彰吾さん、見て!」
と言いながら、
遠くに見える島影を
長い髪を
風になびかせながら
笑顔で指差す沙耶の横顔を
幸せな気分で見つめていた。
後篇終わり。